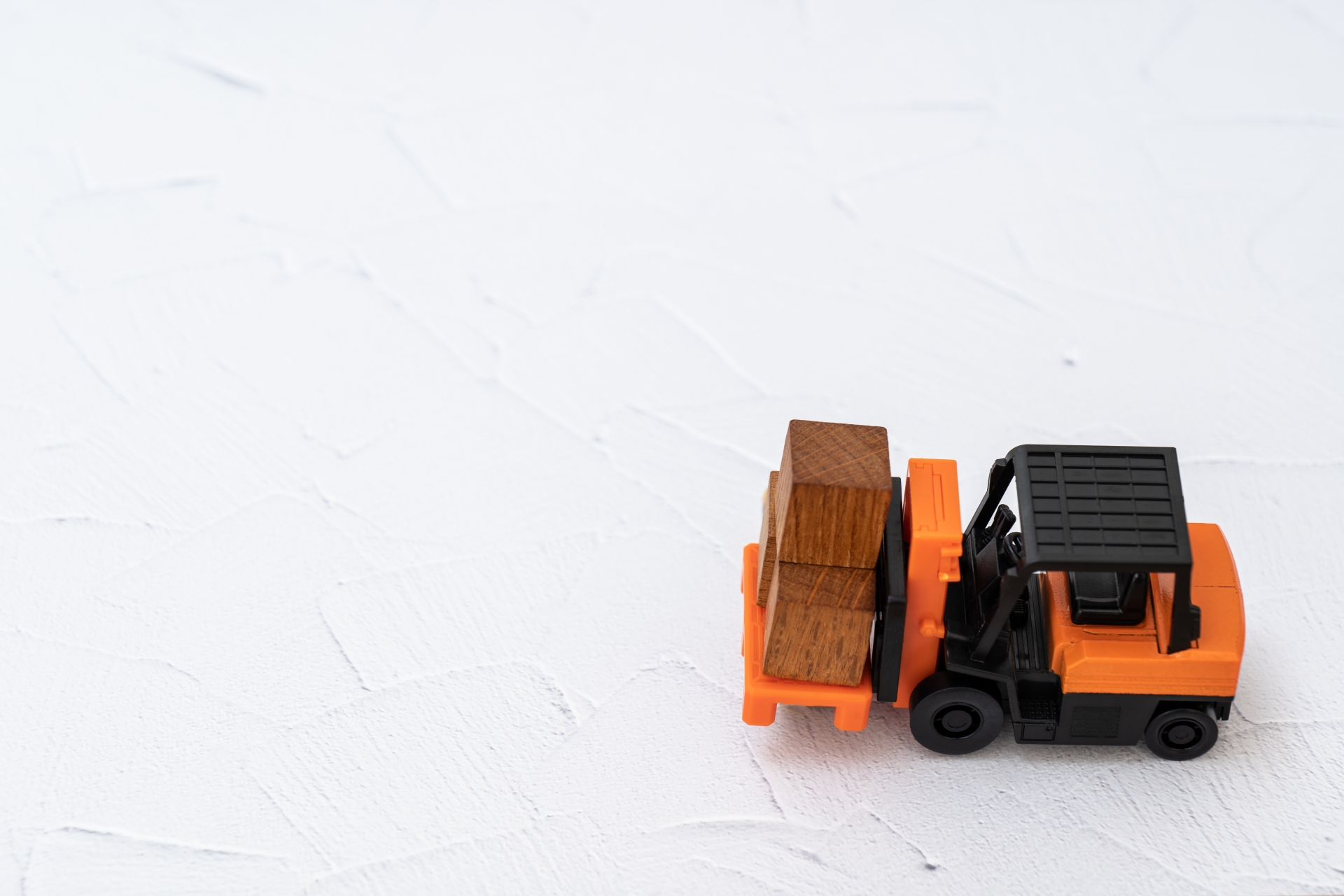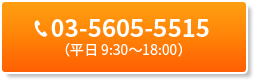VMIとは|物流倉庫におけるメリットや導入事例をわかりやすく解説
公開日:
:
最終更新日:2023/06/09
ファッション物流
大量の商品を抱える小売事業者や店舗にとって、在庫管理は手間のかかる業務のひとつです。また、需要の変化に応じて発注量を検討し、納入業者にオーダーをかけるのも重要な仕事です。
このような問題や課題を解決するために、VMIとよばれる在庫管理手法があります。
本記事では、VMIは小売事業者や店舗、納入業者にとってどのようなメリット・デメリットがあるのか、導入にあたって押さえておきたい注意点などもあわせて解説します。
Contents
VMIとは
VMIとは「Vendor Managed Inventory」の略称で、一言で表現すれば「ベンダー主導型の管理在庫」といえます。
ベンダーとは、製品の売り手業者を指し、一般的には小売店へ商品を納入する業者を意味します。これに対し、製品の買い手業者をバイヤーとよび、一般的にはスーパーやコンビニエンスストア、デパートなどがそれにあたります。
通常の在庫管理では、バイヤーからベンダー側へ商品の発注を行います。しかし、VMIではベンダーがバイヤーの在庫を管理し、必要な量を適切なタイミングで補充するという仕組みで成り立っています。
VMIを成功させるにはベンダーとバイヤーの情報共有や協力が不可欠であり、お互いの信頼関係の上に成り立つシステムといえます。
【EC物流担当者必見】FBAとは?メリット・デメリット、その他倉庫との違いを解説
VMIのメリット・デメリット
VMIはベンダーとバイヤーそれぞれにとってどのようなメリットがあるのでしょうか。また、デメリットとして考えられるポイントも紹介します。
ベンダーにとってのメリット・デメリット
ベンダーにとってのメリットとデメリットは以下の通りです。
| メリット | デメリット |
| ・在庫状況に基づき正確な生産計画を立てやすくなる | ・法令の正しい知識が必要
・ITシステム導入やスタッフのトレーニングなどの初期投資が必要 |
販売店舗にどの程度の在庫があるのか、ベンダーがリアルタイムで把握できることで無駄のない生産計画が立てられるのが最大のメリットといえるでしょう。
これに対し、VMIは下請法をはじめとした法令を遵守しなければならないほか、高額な初期投資も必要になることが多くあります。
バイヤーにとってのメリット・デメリット
バイヤーにとってのメリットとデメリットは以下の通りです。
| メリット | デメリット |
| ・販売機会の損失を防げる
・過剰在庫のリスクを低減できる ・在庫管理業務を減らせる |
・法令の正しい知識が必要
・ITシステム導入やスタッフのトレーニングなどの初期投資が必要 ・ベンダーへ正確なデータを共有できないと在庫管理に影響を及ぼす |
バイヤーにとってのメリットとしては、過剰在庫や在庫切れを防げるほか、在庫管理業務の負担を低減できることが大きいでしょう。
一方、デメリットはベンダー側とも共通していますが、これに加えて正確なデータを共有できないと在庫管理に影響を及ぼすことも重要な点です。
VMIと混同しやすい言葉との違い
物流業界ではVMIのようなさまざまな専門用語がありますが、特に混同しやすい3つの言葉の違いを解説しましょう。
JIT(ジャストインタイム)
JITとは「Just in Time」の略称で、必要なときに必要な量だけ製造・配送するという概念です。
「Just in Time」を日本語に直訳すると「ちょうど良いタイミングで」と表現され、無駄な在庫を持たず、生産や配送を効率化しようとする考え方です。
一見するとVMIと似た概念と捉えられがちですが、VMIはベンダーが主導となって在庫を管理するのに対し、JITではバイヤー側が主導となって在庫管理をするという違いがあります。
CRP
CRPとは「Continuous Replenishment Program」の略称で、「ベンダー主導型センター在庫管理」ともよばれます。
バイヤー側のセンター在庫をベンダーが主導で管理し、在庫が一定の水準に達したら自動的に在庫を補充するという手法です。
バイヤー側とベンダー側の情報共有に基づき、在庫が切れる前に常に補充を行うことからVMIと同じように捉えられますが、CRPの範囲には流通加工なども含まれます。
コンサインメント
コンサインメントとは、ベンダーがバイヤー先に商品を預けておき、商品が売れた時点で初めてベンダーに支払いが発生するという取引方法です。コンサインメントでは、バイヤーが在庫を保有するものの、実際に商品が売れるまではベンダーが所有権を持っています。
VMI倉庫にしたら在庫管理はどうなる?
VMIに対応した専用倉庫をVMI倉庫とよびますが、従来の倉庫と比べて在庫管理にはどのような違いがあるのでしょうか。
一般的な倉庫における在庫管理では、バイヤー側から各ベンダーに対して注文を行い、ベンダーが個別に納品します。これに対しVMI倉庫の場合は、複数のメーカーから発送された商品をVMI倉庫に集約し在庫を確保しておきます。
つねに十分な在庫量をVMI倉庫に確保しておくことで、ベンダーはバイヤーに対してスピーディーな出荷が可能となります。
また、出荷頻度の高い小口配送にも対応しやすくなるメリットもあります。
VMIの導入事例
VMIは主に材料や素材を調達し製品を組み立て、生産する企業に多く採用されています。
具体的にどのような導入事例があるのか、VMIの導入によってどのような効果が得られたのか2社の例をもとに紹介しましょう。
材料調達リードタイムの短縮に成功
各種自動機や検査機器、医療機器などの設計・製作の事業を展開しているメーカーでは、自社が管理するVMI倉庫に材料を保管・管理することで、材料調達のリードタイムを大幅に短縮することに成功しています。
従来の在庫管理手法では2週間から1ヶ月半ほどを要していたものが、VMI倉庫倉庫を導入したことでわずか1日で調達できるようなりました。
VMIの導入にあたっては、今回紹介してきたようにバイヤー側からの正確な在庫情報の共有が課題となりますが、毎日決まった時刻に最新の在庫情報が自動的に配信される仕組みを構築し信頼性を担保しています。
メーカーの生産拠点に隣接したVMI倉庫からJIT納品を実現
大手商社グループの物流会社では、メーカーの生産計画と緊密に連携した材料供給体制を構築するために、メーカーの生産拠点に隣接した場所にVMI倉庫を構えています。
24時間体制で資材在庫などの物流情報を可視化・共有化し、最短1時間ごとのJIT納品を実現しています。
また、在庫情報の記録や在庫シミュレーションを行う専用システムも開発し、材料を調達するサプライヤーや納品先のメーカーともシステムを連携することでシームレスな情報共有を実現しました。
WMSとは?物流における倉庫管理システムの導入メリットを解説
VMI導入時の注意点
VMIの導入にあたっては、ベンダーとバイヤーとの間でさまざまなトラブルが起こることも予想されるため、注意しておかなければならないポイントが存在します。
下請法の遵守
VMIではベンダーがバイヤーの在庫を管理し、必要に応じて補充、バイヤーが必要なときにそれを取得するという形態が一般的です。
このようなVMIの仕組み上、特に注意しておかなければならないのが下請法の遵守です。
下請法(下請代金支払遅延等防止法)では、主契約者が商品やサービスを受け取った後、一定期間内に代金を支払うことを求めています。
ベンダーが在庫を保有しながらも、それがバイヤーに販売されるまで代金が支払われない場合、下請法に抵触する可能性があります。
したがって、VMIを導入する場合には、ベンダーとバイヤーの間で明確な契約を結び、代金の支払いについて公正な取り決めをすることが必要です。
システム化による正確な情報の提供
バイヤー側の在庫情報が適切に共有されていない場合、ベンダーは適切な在庫管理や在庫の補充が難しくなり、両者の信頼関係はなくなってしまいます。
このような事態を防ぐためにも、日々の在庫情報を正確に共有できる仕組みを構築しておかなければなりません。
たとえば、在庫情報システムをベンダーとバイヤー間で共有し、毎日決まったタイミングで情報を反映できる仕組みも有効でしょう。
これにより、精度の高い在庫情報や販売情報が共有できるほか、需要予測の精度向上にも貢献できます。
自動倉庫の導入事例やメリット・デメリットを紹介|アパレル向き?
VMIの導入が向いている企業とは
ベンダーが在庫管理を担うVMIは、どのような企業に適した仕組みといえるのでしょうか。3つの例をもとに紹介します。
需要の変動が大きい企業
季節や天候によって需要が変動する場合、売上の予測が難しく、在庫管理が複雑になりがちです。このような企業にとって、VMIは有効な手段といえます。
在庫管理システムをベンダーとバイヤー間で共有できていれば、バイヤー側からベンダーに対して都度発注をする手間がなくなり、ベンダーは在庫情報をもとに需要の変動に迅速に対応できます。
その結果、在庫過剰や在庫不足を防ぐことが可能となります。
ビジネス規模の大きい企業
大規模な製造企業や小売業者は、多品種の製品を取り扱うため在庫管理が煩雑化しがちです。
日々の発注業務はもちろんのこと、バイヤーにとっては在庫管理業務も膨大で人手が不足することもあるでしょう。
そこで、VMIを利用することにより、発注業務の効率化が実現できるほか、在庫管理の工数とコストも削減でき、生産性向上に貢献できます。
ベンダーと長期的な信頼関係を持っている企業
VMIはベンダーとバイヤー間での強固なパートナーシップが必要不可欠です。
ベンダーとバイヤー間で長期的な取引があり信頼関係が構築されていれば、VMIを導入するための土壌が醸成されており、比較的スムーズに実現できるはずです。
ただし、そのような場合でもVMIの導入がきっかけでトラブルに陥らないよう、明確な契約を結び下請法を遵守することが大切です。
倉庫運営をアウトソーシングするメリット
VMIのように在庫管理を含めた倉庫運営を外部企業にアウトソーシングすることは、バイヤー側にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。
リソースの最適化・分散
倉庫運営をアウトソーシングすれば、自社の経営リソースをコア業務や重要なビジネス活動に集中させることができます。
倉庫運営には多くの人員とコストが必要であり、自社だけで物流体制を構築・維持していくためには大きな負担がのしかかります。
倉庫運営をアウトソーシングすることで、リソースを分散し経営を最適化できます。
ビジネス規模への柔軟な対応
ビジネス規模が急速に成長しているタイミングもあれば、需要の低下によって縮小気味になることもあります。
ビジネスの需要が増減するとき、自社で倉庫を運営しているとリソース不足によって対応が難しくなったり、無駄なコストが発生したりすることも考えられます。
しかし、倉庫運営をアウトソーシングできれば、ビジネスの成長や需要の変動にも容易に対応することができるでしょう。
物流業界におけるコンサルティングのメリットや費用について解説
OTSはアパレル・ファッション・ジュエリーに特化した物流アウトソーシング専門会社
VMIは物流業務を最適化するためにも有効な在庫管理手法ですが、取り扱う商材や品目によっては専門的なノウハウが求められることもあります。
VMIに対応している物流会社でも、特定の商材や品目に関する知識がないと物流業務が最適化されず効果が見込めないこともあるでしょう。
たとえば、アパレルやファッション、ジュエリーなどの品目は季節によっても需要の変動が大きく、適切な在庫管理ができていないと大量の不良在庫を抱えたり、在庫切れによる販売機会の損失を招いたりすることもあります。
これらの商材に特化したVMIを検討している企業は、ぜひ一度OTSへご相談ください。OTSはアパレル・ファッション・ジュエリーに特化した物流アウトソーシングの専門会社であり、VMIをはじめとしたさまざまな在庫管理手法を提案させていただきます。
まとめ
VMIは需要の変動に柔軟に対応したり、バイヤー側の在庫管理の手間を削減したりするための有効な手法のひとつです。
しかし、ベンダーとバイヤー間の信頼関係が構築され、正確な在庫情報が共有できているという前提が不可欠であり、これらが崩れてしまうとVMIそのものが成り立たなくなってしまいます。
また、VMIの導入にあたっては下請法など専門的な知識も把握しておく必要があるため、もし導入にあたって不安や困りごとがある場合には物流アウトソーシングの専門会社へ相談してみましょう。
OTS PR
最新記事 by OTS PR (全て見る)
- 【オーティーエス】2025卒会社説明会開催中 - 2024年3月11日
- 不動在庫(デッドストック)がもたらすデメリットと対処法 - 2023年6月19日
- オムニチャネルとはどんな戦略?メリットを解説|成功事例も紹介 - 2023年6月14日
ブログの読者になる
メールで受け取ることができます。
関連記事
-

-
2015年も大変お世話になりました。
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部
-

-
棚卸しを行う目的とは|手順や方法・時期を解説
 OTS PR
OTS PR
-

-
分譲マンション販売から見る物流倉庫の考察
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部
-

-
在庫管理における定期発注方式と定量発注方式の違いを解説
 OTS PR
OTS PR
-

-
5Sって、自分が『楽』になればいいだけ
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部