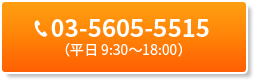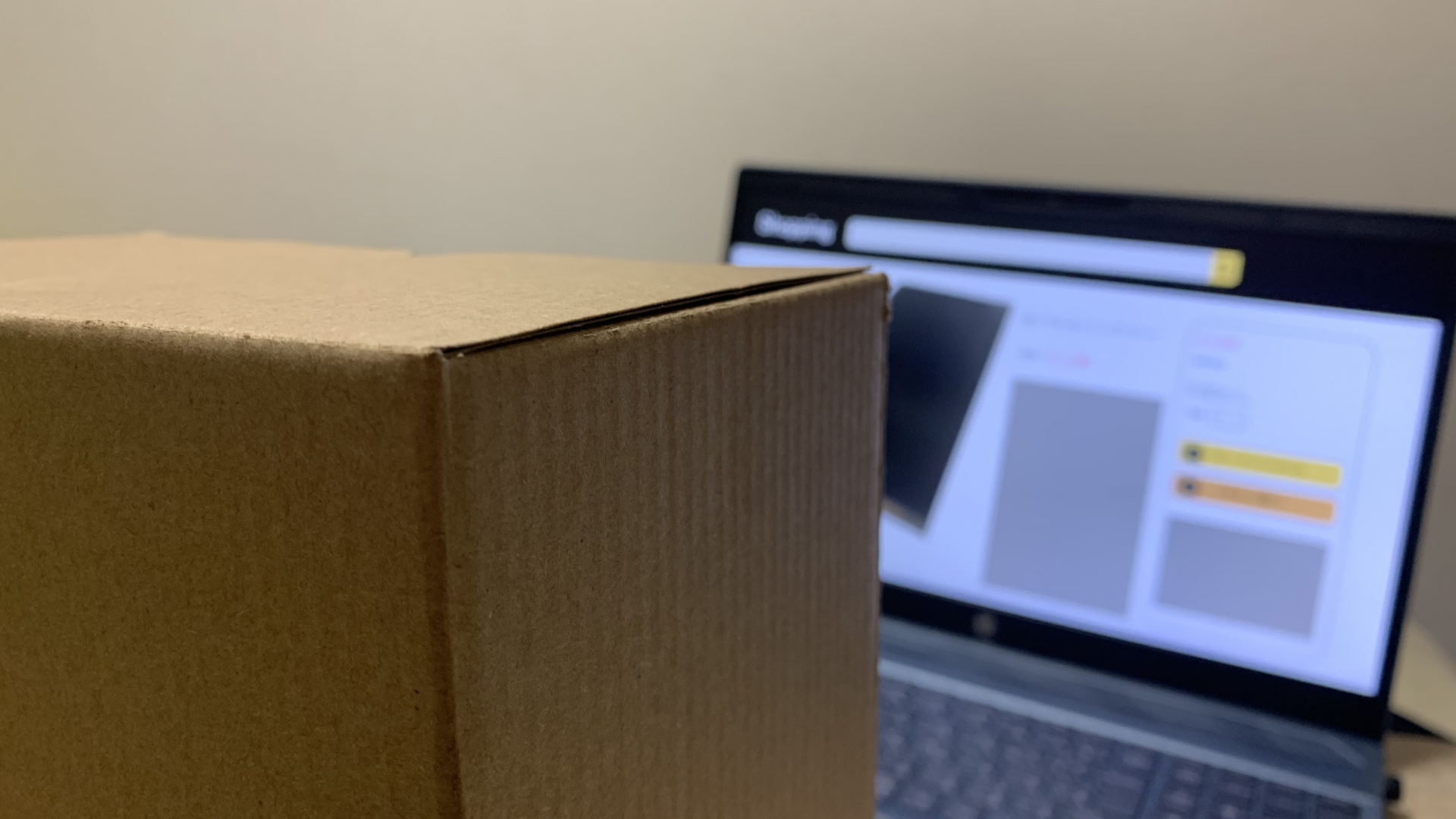物流代行サービスの発送代行業者の選び方|費用やメリットについて
公開日:
:
最終更新日:2023/06/08
ファッション物流
大量の荷物の発送や在庫管理などに頭を悩ませている企業も多いのではないでしょうか。物流の問題を解決するために、物流代行サービスが昨今注目されています。
本記事では、物流代行サービスとはどういったものなのか、活用するメリットとデメリット、信頼できる物流代行業者の選び方などもあわせて紹介します。
Contents
物流代行サービスとは
物流代行サービスとはその名の通り、荷物の保管や在庫管理、ピッキング、梱包といった物流業務を荷主企業に代わって行うサービスのことです。
物流代行サービスを提供している企業は物流専門の企業であり、荷主企業にはない物流に関する専門的なノウハウや豊富なリソースを活用できます。
物流業務でよくある課題や悩み
物流代行サービスを利用する荷主企業が多い背景には、物流業務に関するさまざまな悩みを抱えていることが挙げられます。
具体的にどういった悩みが多いのか、代表的なものをいくつか紹介しましょう。
在庫保管場所がない・狭い
物流業務では在庫を保管しておく場所や設備が不可欠です。しかし、自社で物流倉庫を構えるとなると土地を確保し膨大なコストをかけて倉庫を建設しなければなりません。
倉庫を借りるという方法もありますが、自社の物流規模にマッチした面積の倉庫がなかなか見つからないという企業も少なくありません。
スタッフの数が足りない
物流業界は深刻な人手不足に陥っており、自社で物流体制を構築しようと考えてもスタッフの数が確保できないというケースがあります。
また、スタッフが採用できたとしても人件費が増大し、物流コストの上昇によって経営を圧迫するリスクも考えられます。
物流業務に関するノウハウがない
物流業務の経験がない荷主企業にとって、一から自社物流の体制を構築しようとすると膨大な時間とコストがかかってしまいます。
実務の経験がない状態で一からノウハウを取得することは現実的ではなく、自社物流の体制を整えるまでに時間を要します。
物流の2024年問題を簡単解説|働き方関連改革法が物流業界に与える影響
物流代行と発送代行の違い
物流代行と似たサービスとして、発送代行があります。ともに荷主企業の物流業務を支援するという目的がありますが、業務内容と範囲には違いがあります。
まず、物流代行は荷物の輸送や保管、在庫管理、ピッキング、包装、配送、返品といったように、物流業務全体を受託します。
これに対し発送代行は、製品の配送業務のみを代行するサービスです。商品の梱包、配送ラベルの作成、配送業者との連絡、商品の配送などが含まれ、荷物の輸送や保管、在庫管理、返品などの業務には対応しないという違いがあります。
物流代行サービスのメリットとデメリット
物流業務を効率化するために便利な物流代行サービスですが、メリットばかりではなくデメリットもあります。
メリット
物流代行サービスを利用する主なメリットは以下の3点です。
物流業務の効率化が図れる
物流代行サービスは物流業務のノウハウや経験が豊富な専門会社が提供するため、業務そのものの効率化が図れます。それまで物流業務を担当してきたスタッフは製品開発やマーケティング、営業といった業務に専念でき、生産性向上が期待できるでしょう。
ビジネス規模に応じて利用できる
物流代行サービスはビジネス規模の拡大や縮小にも柔軟に対応できます。急速な成長を遂げ荷物の取扱量が増えた場合でも、物流代行サービスの契約内容や契約プランを見直すことができ、無駄なコストがかかる心配がありません。
トータルコストの最適化
自社物流を構築するために倉庫や設備を用意し、スタッフも一から教育するとなると莫大なコストと時間を要します。
しかし、物流代行サービスを利用すればそのような準備が不要で、トータルコストを最適化することもできるでしょう。
デメリット
物流代行サービスを利用する主なデメリットは以下の2点が考えられます。
業務内容のカスタマイズが難しい
物流代行サービスを依頼する際には、業務内容をマニュアル化しておかなければなりません。イレギュラーな対応や高度な判断が求められる特殊な業務はマニュアル化が難しく、全ての業務を委託できない可能性もあります。
業者によって作業品質にばらつきがある
物流代行サービスはさまざまな業者が提供していますが、すべての業者が画一的な作業品質を提供できるとは限りません。
特に取り扱う商材や荷物の量などによっても、業者によって得意・不得意なケースがあります。
そのため、物流代行サービスを依頼する際には信頼できる業者を見極めることが必要です。
物流代行サービスは個人のEC出品者や小規模事業者でも利用できる?
物流代行サービスと聞くと、大手メーカーや小売事業者などの法人のみが契約できるものと考える方も少なくありません。
しかし、実は物流代行サービスは個人でECサイトへ出品している方や、小規模事業者なども含めてビジネス規模に関わらず手軽に利用できます。
大手企業を中心に展開している業者もあれば、個人や小規模事業者をメインターゲットにサービスを展開している業者もあります。
物流代行サービスを利用すべき事業者の特徴
物流代行サービスのメリットを最大化するためには、自社がサービスの利用に向いているのかを判断する必要があります。そこで、具体的にどのような事業者に物流代行サービスは向いているのか、いくつか特徴を紹介しましょう。
コア業務に集中し生産性を向上させたい事業者
物流業務に多くの人員が割かれ、製品開発やマーケティング、営業などに手が回っていない企業にこそ物流代行サービスはおすすめです。
自社物流のノウハウを得るために自社のスタッフが業務を担うことは大切ですが、それが原因でコア業務に支障をきたすようでは本末転倒です。
製品開発やマーケティング、営業などは自社の売上や利益を支えるエンジンのようなものであり、重点的に人材をアサインするためにも物流代行サービスは有効です。
人手不足に悩んでいる事業者
自社物流を支える作業スタッフを採用するために、求人情報を出してもなかなか候補者が集まってこない企業も多いのではないでしょうか。
物流代行サービスを活用することで、外部企業の専門人材に業務を任せられ、人手不足の問題を一気に解決できます。
取り扱い商品数や種類が多い事業者
事業の成長にともない、取り扱う製品の数や種類が増えていくと在庫管理や発送業務が煩雑化し、ときには誤配送などが発生する可能性もあるでしょう。
このような事故を防ぐためにも、専門的なノウハウをもとに正確かつスピーディーな作業を提供してくれる物流代行サービスは心強い存在です。
【物流を始めたい方必見】レンタル倉庫を借りる方法や費用を解説
物流代行サービスにかかる費用相場
物流代行サービスの利用にあたり、多くの方にとって気になるのがコストの問題ではないでしょうか。
物流代行サービスを提供する企業によっても費用の内訳や金額は異なりますが、相場としては以下のような金額となっています。
- システム利用料(3~10万/月)
- 倉庫保管料(月額4,000〜10,000円/坪)
- 入庫・検品料(10〜150円/個)
- ピッキング料(10〜150円/個)
- 梱包料(費)(100円〜/個)
- 配送料(費)(500円〜/個)
配送費だけで見れば一般的な宅配事業者に比べてわずかに安価ですが、それ以外にもシステム利用料や倉庫保管料などさまざまな費用が発生します。
また、倉庫保管料は倉庫の立地や面積によっても坪単価は異なり、特に都心部に近く面積が大きい倉庫ほど高額になる傾向が見られます。
物流代行サービスを利用するまでの流れ
物流代行サービスの利用にあたり、どのような流れで運用がスタートするのでしょうか。一連の流れを見てみましょう。
1.物流代行サービス事業者の選定
まずは自社のニーズに合う物流代行サービスを探します。
自社の物流業務のなかでどういった課題・問題を解決したいのかを検討し、自社が取り扱う荷物の品目や量に対応できる事業者を探しましょう。
また、どのような物流業務を代行してもらえるのか、料金や信頼性、サービスの評判なども比較検討します。
2.打ち合わせ・見積もり
物流代行サービス事業者と打ち合わせを行い、見積もりを取得します。
打ち合わせでは、どのような品目の荷物をどの程度扱うのか、依頼したい業務内容なども細かく相談しておきましょう。
また、見積内容を確認のうえ、詳細が分からない内訳や金額があれば納得のいく回答が得られるまで質問をしてください。
3.契約
打ち合わせおよび見積もりの内容に問題がなければ、物流代行サービスとの契約を結びます。契約内容には、サービスの範囲、料金、契約期間、解約条件などが含まれるため、これらに誤りがないかをしっかりと確認しておきましょう。
4.システム導入・連携
物流代行サービスが運用するシステムと、自社が運用しているシステムとの連携を設定します。
これにより、受注データの送受信や在庫情報の共有などがスムーズに行えるようになります。
5.在庫の移動・サービス開始
システムの導入・連携が完了したら、いよいよ自社の在庫を物流代行サービスの倉庫に移動し運用開始となります。
6.評価・フィードバック
サービス品質を定期的に評価し、フィードバックを行います。運用にあたって解決すべき問題や課題が見えてきた場合には、代行事業者と協議のうえ必要に応じて改善策を講じます。
通販(EC)物流サービスとは?特徴や一般的な物流サービスとの違いを解説
物流代行業者を選ぶポイント
物流代行サービスを提供している企業は数多く存在するため、信頼できる事業者が見つけられず困っている方も多いのではないでしょうか。
そこで、物流代行サービスを選ぶうえで押さえておきたいポイントを3つ紹介します。
扱う荷物に対する専門性
まず、物流代行業者が特定の商材や商品カテゴリに精通しているかをチェックしましょう。たとえば、食品や医薬品などの場合、厳密な温度管理が求められ在庫管理には専門的なノウハウが求められます。
また、アパレル商品やファッション小物などは同じ品目でも複数のサイズやカラーバリエーションがあり、在庫管理が煩雑化しがちです。
このように、物流業務に特殊なノウハウが求められる場合には、その分野の経験が豊富な業者を選ぶ必要があります。
最新技術を積極的に取り入れているか
物流業務の効率化を図るうえでは、物流代行業者が最新の技術を活用しているかも確認しておきましょう。
たとえば、リアルタイムで在庫情報を共有できる在庫管理システムや、配送状況を追跡できる配送管理システムなどがあれば、物流管理にかかる工数やコストを最小限に抑えられ、生産性向上にも貢献できます。
サポート品質
物流業務では人為的ミスによる誤配送や、天候や交通機関の影響で配送遅延などが発生することがあります。
このような事態に陥ったときでも、適切かつ柔軟に対応してくれるかどうかも重要な選定ポイントです。
物流代行サービスの発送代行業者の選び方|気になる費用相場やメリットも解説
OTSは徹底した品質管理と物流業務をサポート
アパレル製品やファッション小物などを扱うメーカーや小売事業者、ECサイト出品者のなかには、大量の在庫を抱え管理が煩雑化し頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
また、一から自社物流の体制を構築しようと考えているものの、物流業務のノウハウがなくなかなか進まないというケースも少なくありません。
もし、このようなお悩みを抱えている事業者は、物流アウトソーシングの専門業者であるOTSへご相談ください。
OTSはアパレル・ファッション・ジュエリーといった品目の物流を専門に行っており、物流業務にお悩みのメーカーや店舗に対してコンサルティングやアウトソーシングサービスを提供しています。
物流業務の円滑化や効率化を実現したい企業はもちろんのこと、物流の品質向上にも貢献できるため、まずは一度お問い合わせください。
まとめ
荷物の保管や在庫管理、ピッキング、梱包といった物流業務を荷主企業に代わって行う物流代行サービスは、人手不足の解消や経営効率の改善を目指す多くの企業に選ばれています。
物流代行と聞くと、大手メーカーや大規模な小売事業者でなければ利用できないのではないかと不安を覚える方も多いですが、実際には小規模事業者や個人でも手軽に利用できるサービスもあります。
自社が抱える物流業務の問題や課題を解決し、生産性を向上させるためにもぜひ物流代行サービスの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
OTS PR
最新記事 by OTS PR (全て見る)
- 【オーティーエス】2025卒会社説明会開催中 - 2024年3月11日
- 不動在庫(デッドストック)がもたらすデメリットと対処法 - 2023年6月19日
- オムニチャネルとはどんな戦略?メリットを解説|成功事例も紹介 - 2023年6月14日
ブログの読者になる
メールで受け取ることができます。
関連記事
-

-
海外リユース事業の可能性
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部
-

-
分譲マンション販売から見る物流倉庫の考察
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部
-

-
「物流会社のミッションは?」
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部
-

-
【アメリカ出張旅行記②】
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部
-

-
リアル体験 欲しいものが手に入らない・・・・
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部