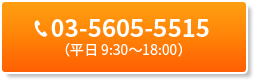リードタイムとは|意味や短縮方法、納期との違いを解説
公開日:
:
最終更新日:2023/04/26
ネット通販
商品を製造するメーカーや、エンドユーザーへ販売する小売事業者などにとって、リードタイムは重要な経営指標のひとつに挙げられます。
リードタイムという言葉を一度は耳にしたことがある方も多いと思いますが、正確な意味を理解できている方は意外と少ないものです。
そこで本記事では、物流におけるリードタイムとはどういった意味を表すのか、誤解されがちな納期との違い、リードタイムを短縮するために企業ができることなどもあわせて解説します。
Contents
リードタイムとは
リードタイムとは、工程のスタートからゴールまでにかかる時間や日数のことを指します。
一般的には物流業界で用いられている言葉であり、商品を注文した時点から、エンドユーザーの手元に到着するまでの時間・日数を指す場合が多いです。
メーカーや小売事業者がユーザーからの注文を受けた後は、商品を用意したり取り寄せたりする必要があるほか、輸送にかかる時間なども考慮しなければなりません。
また、注文を受けてから商品の製造に取り掛からなければならない場合には、製造や組立にかかる時間もリードタイムに含まれます。
リードタイムは顧客満足度にも大きく影響することから、物流体制の確保や生産計画などの立案において重要な指標のひとつとなります。
先入先出法をわかりやすく解説|メリット・デメリットと活用事例を紹介
リードタイムと納期の違い
リードタイムと混同しやすい言葉に納期があります。
冒頭でリードタイムとは「商品を注文した時点からエンドユーザーの手元に到着するまでの時間」と紹介しました。
これに対し納期とは、「注文した商品がエンドユーザーの手元に届く日付」のことを指します。
たとえば、3月1日に注文を受けた商品が、3月4日に届く場合にはリードタイムは「3日間」ですが、納期は「3月4日」と表すことができます。
リードタイムも納期も似たような概念で紛らわしいと感じる方も多いですが、両者は密接に関連しています。
メーカーや小売事業者、物流事業者にとっては、注文を受けてから発送、到着までのプロセスを管理するために、リードタイムを明確にする必要があります。
一方、エンドユーザーにとっては、「リードタイムは3日間」と聞いても具体的な日付を計算しなければならず手間がかかります。
また、エンドユーザーのなかには「◯月◯日までに配送してほしい」といった要望を上げることもあるでしょう。
エンドユーザーと事業者の認識の相違を防ぐためにも、「◯月◯日到着」といったように納期を明確に定義しておく必要があるのです。
リードタイムの種類
一口にリードタイムといっても、じつはさまざまな種類があり用途や場面に応じて使い分けられることがあります。
今回は5種類のリードタイムとそれぞれの違いを解説しましょう。
製造リードタイム
製造リードタイムとは、商品の製造から完成までに要する時間・日数を指します。
複雑なプロセスを経る製品ほど製造リードタイムは長くなりがちで、ほかにも設備の充実度や材料調達の難易度など、さまざまな要素によって変わってきます。
生産リードタイム
生産リードタイムは、メーカーや企業が製品の生産オーダーを受けた後、製品が完成し生産拠点から商品が出荷されるまでに要する時間・日数を指します。
製造リードタイムと似ていますが、生産リードタイムは商品が完成し実際に出荷されるまでの時間・日数も含まれるという違いがあります。
調達リードタイム
調達リードタイムとは、商品の製造に必要な原材料を調達するために要する時間・日数を指します。
材料調達先が国内か海外かによっても変わるほか、調達方法(トラックor空輸or船便など)によっても調達リードタイムは変動します。
出荷リードタイム
出荷リードタイムは、物流センターや倉庫から商品をピッキング・梱包し、トラックへ積み込むまでの時間を指します。
物流センターで働くスタッフの数やスキル、取り扱う商品の種類や数、繁忙期・閑散期などの要因によっても出荷リードタイムは変わってきます。
配送(輸送)リードタイム
配送リードタイムとは、商品を出荷してからエンドユーザーが受け取るまでの時間・日数を指します。
輸送リードタイムとよばれることもあります。
配送先の場所が遠いほど配送リードタイムは長くなる傾向があるほか、運送会社との契約や配送方法、交通状況などによっても変わることがあります。
リードタイムを短縮するメリット
リードタイムが短いほどメーカーや事業者にとっては業務負担が増すことを意味しますが、それ以上にメリットがあることも事実です。
いち早くエンドユーザーに商品を届けられるため顧客満足度が向上するといった点が代表的ですが、それ以外にどういったメリットが考えられるのか、企業の目線で考えてみましょう。
在庫管理コストの削減
リードタイムが長いということは、それだけ長期間にわたって在庫を管理しなければならないことも意味します。
在庫を保管する期間が長いと、それだけ多くの保管スペースを確保しなければならないほか、在庫管理のための業務負担も増大します。
リードタイムを短縮できれば、最小限の在庫スペース確保と効率的な在庫管理が実現でき、コスト削減につなげられます。
生産効率の向上
リードタイムの短縮は生産プロセスの効率化にもつながります。
たとえば、調達リードタイムが短縮できれば生産に必要な原材料をスピーディーに調達でき、生産ラインの停止時間を減らし生産効率が向上できるでしょう。
短期間でより多くの商品を生産できるようになれば、在庫切れや完売に伴う販売機会の逸失を防げ、売上や利益率もさらに向上していくと期待されます。
他社との差別化
リードタイムが5日間のA社と、3日間のB社があった場合、同じ製品を購入するのであれば多くのエンドユーザーはB社を選ぶでしょう。
リードタイムを短縮することで競合他社よりも早く商品を届けられ、自社の競争力を高めることにもつながります。
また、「最短◯日配送」といったマーケティング戦略を展開することにより、新規顧客の獲得やブランドイメージの向上にもつながる可能性があるでしょう。
リードタイムの計算方法
リードタイムの算出にあたっては、大きく分けて「固定リードタイム計算」と「変動リードタイム計算」という2つの方法があります。
それぞれの計算方法を詳しく解説しましょう。
固定リードタイム計算
固定リードタイム計算とは、商品ごとに固定で設定したリードタイムをもとに計算する方法です。
納期−(リードタイム+安全リードタイム)=予定開始日
上記にある「安全リードタイム」とは、想定されるリードタイムの誤差を考慮し予備として設定する時間・日数を指します。
たとえば、リードタイムが3日間、安全リードタイムを1日と設定していた商品Aを、エンドユーザーから3月5日の希望納期で注文を受けた場合には、以下のように3月1日が予定開始日となります。
3月5日−(3日+1日)=3月1日
変動リードタイム計算
変動リードタイム計算とは、注文を受けた商品の数量やロットに応じてリードタイムを計算する方法です。
納期-〔(待ち+段取り+後処理+移動)+オーダーの所要量×1個当たりの実作業時間〕=予定開始日
上記に示した式のうち、「待ち+段取り+後処理+移動」の項目は品目ごとに固定で考えますが、これに1個当たりの実作業時間も考慮したうえで算出します。
リードタイムの短縮方法
顧客満足度の向上や他社との差別化、在庫管理コストの削減などのメリットを最大化するために、どのようにしてリードタイムを短縮すれば良いのでしょうか。
押さえておきたい3つのポイントに分けて解説します。
リードタイムの可視化
ひとつ目のポイントは、リードタイムを可視化し各プロセスに要している時間や日数を正確に把握することです。
他社と比較して自社のリードタイムが長い場合には、全体を見ただけではどこがボトルネックになっているのか把握しづらいものです。
そこで、製造リードタイムや生産リードタイム、調達リードタイム、出荷リードタイム、配送リードタイムなどのプロセスごとに可視化することで、改善すべきポイントが具体的に見えてきます。
サプライチェーンの最適化
2つ目のポイントは、サプライチェーン全体を見直し最適化を図ることです。
たとえば、原材料や部品を供給するメーカー・取引先と交渉したり協業したりすることで調達リードタイムを短縮できるでしょう。
また、物流事業者と契約形態を見直したり、個別に交渉したりすることで、配送リードタイムの短縮を実現できることもあります。
生産プロセスの見直し
サプライチェーンそのものに問題がない、または改善が難しい場合には、自社の生産プロセスを見直すこともポイントのひとつです。
たとえば、現在手作業で行っている生産プロセスの一部をシステム化する余地はないか、設備の更新によって生産能力の向上を図れないかなど、効率化できる部分を具体的に検討してみましょう。
EC・通販におけるリードタイムの重要性
顧客に商品を届けるという意味では、さまざまなメーカー・企業・店舗にとってリードタイムの短縮は共通の課題といえるでしょう。
なかでも特に重要視されているのが、近年ユーザー数が増えているECや通販の分野です。
ECや通販は自宅にいながらでも手軽に商品をオーダーできますが、実店舗とは異なり商品が手元に届くまで時間を要します。
エンドユーザーの多くは「今すぐにこの商品が欲しい」と感じており、リードタイムが長くなればなるほどストレスや不満を抱えてしまいます。
そのため、ECや通販事業者にとってリードタイムの短縮は顧客満足度に直結する重要な要素といえるのです。
あまりにもリードタイムが長くなってしまうと、他社のサイトにエンドユーザーが流れてしまい、商品のキャンセルやリピート率の低迷を招くことも考えられます。
物流アウトソーシングの上手な選び方|導入メリットや自社物流との違い
OTSはアパレル・ファッション・ジュエリーに特化した物流アウトソーシング専門会社
ECや通販サイトではさまざまな商品が販売されていますが、特にアパレルやファッション、ジュエリーといった製品のニーズは高い傾向にあります。
しかし、これまで実店舗でアパレル製品を扱ってきた小売事業者が、ECや通販へ参入しても物流業務のノウハウがなく、結果としてリードタイムが長くなってしまうこともあります。
リードタイムを短縮することの重要性は理解していても、何から始めれば良いのか分からないケースも多いでしょう。
そのような場合には、物流アウトソーシングの専門会社へ相談してみるのもおすすめです。
OTSはアパレルやファッション、ジュエリー製品に特化した物流業務のアウトソーシングを提供しており、これまでメーカーや卸売業者、小売事業者などへの支援実績があります。
リードタイムを短縮しエンドユーザーからの信頼を勝ち取りたい、他社との優位性を向上させたいと考えている事業者は、ぜひ一度OTSへご相談ください。
まとめ
リードタイムとは、商品を注文してからエンドユーザーの手元に到着するまでの時間・日数を指します。
リードタイムを短縮することは、顧客満足度を向上させるだけでなく、在庫管理コストの削減や他社との差別化にもつながるため、企業にとっては重要な指標であることは間違いありません。
しかし、リードタイムを短縮させることは決して簡単ではなく、さまざまな物流ノウハウが不可欠です。
今回の記事でも紹介してきたように、まずは現状どの程度のリードタイムを要しているのかを可視化したうえで、サプライチェーンの最適化や生産プロセスの見直しなど、具体的な対策をスタートさせていきましょう。
もし、物流ノウハウがなく自社だけで対応が難しい場合には、物流アウトソーシングの専門会社であるOTSへぜひ一度ご相談ください。
OTS PR
最新記事 by OTS PR (全て見る)
- 【オーティーエス】2025卒会社説明会開催中 - 2024年3月11日
- 不動在庫(デッドストック)がもたらすデメリットと対処法 - 2023年6月19日
- オムニチャネルとはどんな戦略?メリットを解説|成功事例も紹介 - 2023年6月14日
ブログの読者になる
メールで受け取ることができます。
関連記事
-

-
エンドユーザーに商品をおとどけするために:上
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部
-
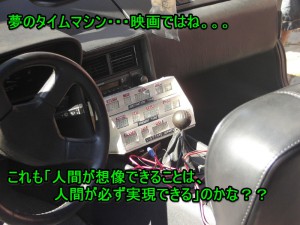
-
有名映画→未来30年後の世界での実現度は?
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部
-

-
ファッション業界とテクノロジー (前編)エアークローゼット
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部
-
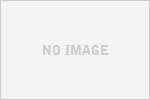
-
物流ってすごいかも・・・って感じた瞬間 ベスト5
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部