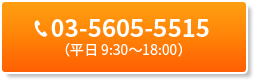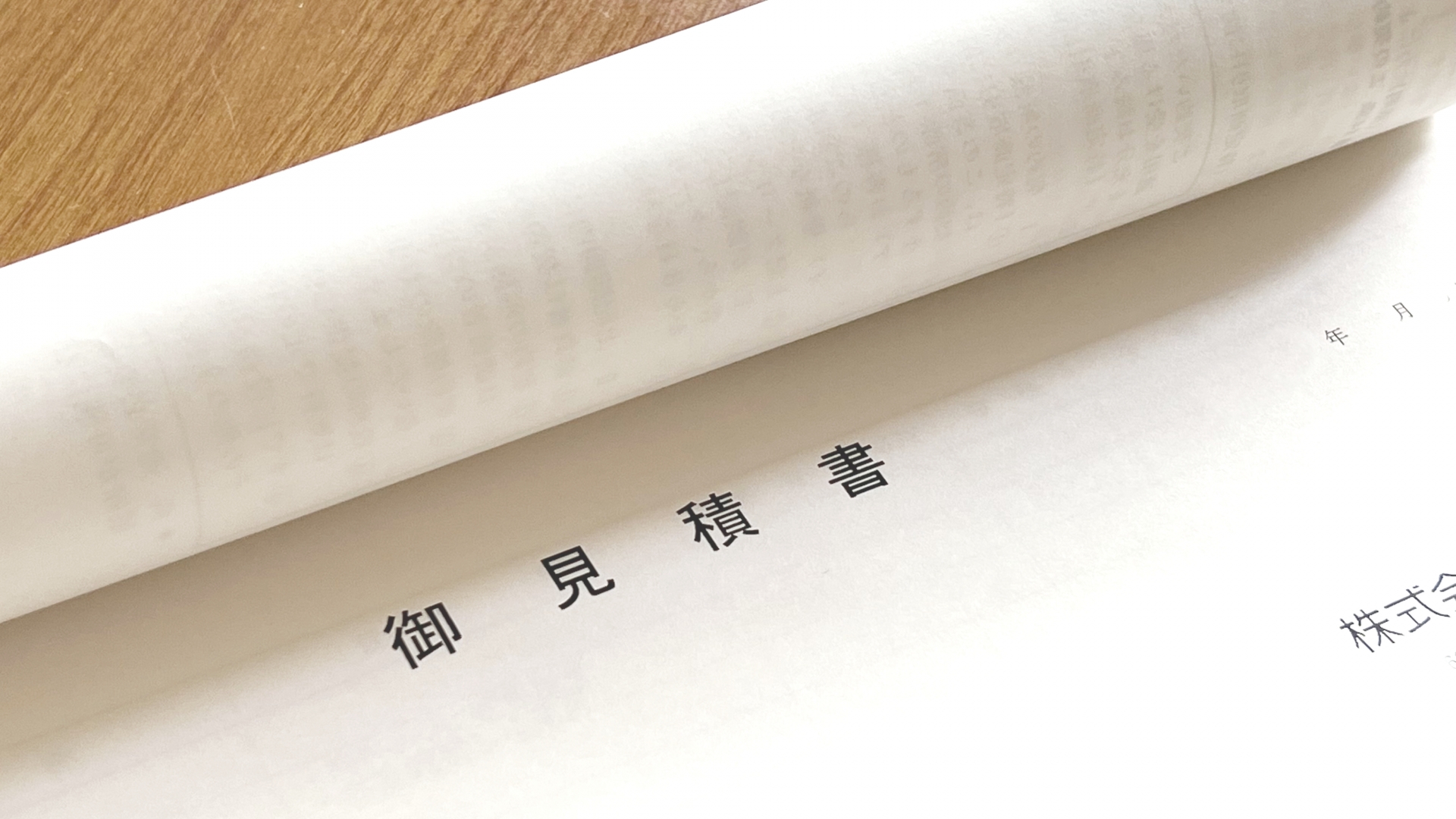受注管理システムとは?|導入メリットやシステム選定のポイントも解説
物流体制を構築・維持するためにはさまざまな業務があり、受注管理もそのひとつに挙げられます。
その名の通り商品の受注情報を適切に管理する業務ですが、オーダーの数が増えるほど業務の負担は増大してしまいます。
このような問題を解決するためのツールとして、受注管理システムがあります。
手作業での受注管理と比較しどのようなメリットがあるのか、具体的にどういった業務を自動化・効率化できるのか、システム選定のポイントなどもあわせて解説します。
Contents
受注管理システムとは
受注管理システムとは、顧客からの注文情報を効率的に管理するためのソフトウェアおよびシステムのことを指します。
受注管理システムを導入することにより、注文情報をシステム上で一元的に管理できるほか、注文の受け入れから発送までの業務を迅速かつ正確に処理することができます。
なお、受注管理システムでは注文情報以外にも、顧客情報や在庫管理の情報、発送情報などさまざまな情報が含まれます。
これらの情報をシステム上で把握することで、納期管理や在庫管理などの業務も円滑に行えるようになります。
さらに、受注管理システムは複数チャネルからの注文を一元的に管理できることも特徴です。電話やFAXによる注文のほか、オンラインストアやメールなどからの注文にも対応できます。
ビジネスの効率化や顧客満足度の向上、生産性向上などのために、多くの物流現場において受注管理システムは活躍しています。
物流アウトソーシングの上手な選び方|導入メリットや自社物流との違い
受注管理に多い課題・悩み
受注管理を行うには、必ずしもシステムを導入しなくても手作業で行うことは可能です。
それにもかかわらず、なぜ導入・運用コストをかけてまで受注管理システムを導入する企業が多いのでしょうか。
その背景には、受注管理を行うにあたって企業が抱えているさまざまな課題や悩みがあります。
どういった課題や悩みを抱えていることが多いのか、代表的なものをいくつか紹介しましょう。
人手不足
現在、多くの企業では深刻な人手不足に陥っており、特に物流業界はその傾向が顕著です。
受注の件数が増えるほど受注管理の業務負担も増大し、手が回らなくなることもあるでしょう。
その結果、長時間労働に陥り、退職者の増加や求人を出しても人が集まらないといった事態にもなりかねず、さらに人手不足を招き悪循環に陥ってしまいます。
短納期のオーダーに対応できない
受注管理業務を人手に頼っていると、書類への手書きや書類管理の業務が煩雑化してしまいます。
それだけでなく、受注から出荷までの間にタイムラグが生じてしまうため、通常納期よりも早く納品してほしいといった短納期に対応できなくなることも考えられます。
柔軟な対応ができないと顧客からの信頼を失ってしまい、継続的な受注が難しくなるケースもあるでしょう。
人為的ミスの発生
物流業務のノウハウがない状態で受注管理を行っていると、書類の不備や漏れ、さらには受注そのものを忘れてしまうなど人為的なミスが発生するリスクもあります。
人間である以上は完全に人為的ミスをなくすことはできませんが、あまりにもミスが多いと企業として信用を失い、経営にも影響を及ぼす可能性があるでしょう。
受注管理の業務内容
そもそも受注管理とは、顧客からの注文情報を管理する業務全般を指します。
しかし、これだけでは抽象的であり、物流業務のノウハウや知見がない企業・担当者にとっては具体的なイメージが湧かないこともあるでしょう。
そこで、受注管理にはどういった業務があるのか、いくつか具体例を交えながら紹介します。
見積もりの作成
取り扱う商品や商材によっては、顧客から正式なオーダーを受ける前に見積書を作成し提示しなければならないことがあります。
過去に何度か取引がある顧客であれば、オーダーのたびに見積書の提出が求められることは少ないでしょう。
しかし、初めて取引をする顧客や取引の頻度が少ない顧客の場合、正式なオーダーの前に見積書が求められることが一般的です。
見積書の作成も受注管理業務のひとつであり、作成した見積書は自社でも適正に管理しておかなければなりません。
注文内容の登録
顧客から正式なオーダーがあった際には、注文内容を正確に把握できるよう情報を登録・管理しておく必要があります。
この際、単に商品名や数量だけを記録するのではなく、顧客情報や希望納期などさまざまな情報もあわせて登録しておかなければなりません。
在庫確認・納期の連絡
注文内容の登録が完了したら、対象の商品がすぐに発送できる状態にあるか在庫を確認します。
取り扱う商品の種類や数量が限られている場合には、倉庫や在庫保管場所を目視で確認すれば済むでしょう。
しかし、事業規模が大きくなっていくと、ひと目見ただけでは在庫の有無や数量を確認することが難しくなります。
そこで、受注管理とあわせて在庫管理も適正に実施しておく必要があるのです。
オーダーを受けた商品の在庫が確認できたら、顧客に対して正式な納期を連絡することも受注管理業務のひとつです。
受注伝票の作成
顧客から商品の受注を受けた後、商品の発送作業に入る前に受注伝票を作成しておく必要があります。
受注伝票とは、オーダーのあった商品名や型番、受注日、納品予定日、金額、納品先の情報などが記載された書類のことです。
受注伝票の作成も受注管理の重要な業務であり、受注漏れをなくすだけでなく決済の管理などにも役立てられます。
注文請書の作成
受注業務の一環として、注文請書を作成・発行する企業も存在します。
注文請書とは、顧客からのオーダーを確実に受注した旨を確認するための書類です。
注文請書は必ずしも発行しなければならないというものではなく、注文請書を発行する代わりにメールなどで「注文を承りました」というメッセージを送信する企業も少なくありません。
受注管理システムの導入メリット
上記で紹介した受注業務を効率化・自動化することを目的として、受注管理システムを導入する企業は少なくありません。
しかし、コストをかけて導入する以上は受注管理システムのメリットを正確に把握しておくことが大切です。
システム導入によって企業はどういったメリットが得られるのか、3つのポイントに絞って解説しましょう。
人的ミスや人件費が削減できる
ひとつ目は、自動化によって人手が削減され、人為的なミスも低減できるという点です。
たとえば、見積書の作成を例にとっても、手作業の場合は顧客情報や商品名、数量、金額などを正確に入力しなければならず手間がかかります。
しかし、受注管理システムの導入によってこれらの業務を自動化でき、入力ミスや漏れを大幅に低減できます。
見積書の作成以外にも注文内容の登録や在庫確認・納期の連絡、受注伝票や注文請書の作成などが受注管理システム上で自動化され、人手不足に悩む企業も限られたスタッフで業務を回すことができるでしょう。
他のシステムとデータ連携ができる
受注管理業務のなかでも紹介しましたが、一連の業務を行うためにはさまざまなデータ、情報が必要です。
たとえば、在庫確認では在庫情報を把握しておかなければならないほか、受注伝票や見積書の作成には顧客情報や商品情報なども不可欠です。
特に取り扱う商品の数や種類が多い企業・店舗では、手作業での在庫管理が難しいため在庫管理システムを導入しているところも少なくありません。
また、個人の顧客を相手に事業を運営している場合には、顧客情報=個人情報であり、厳重な管理が求められます。万が一書類を紛失したり外部に漏えいしたりといったリスクを最小限に留めるためにも、顧客情報をシステム上で管理しているケースも多いでしょう。
受注管理システムを導入することで、在庫管理システムや顧客管理システム、商品情報のデータベースといったさまざまなシステムとデータ連携ができるようになります。
顧客の満足度が向上する
受注管理システムの導入は、業務効率化や生産性向上といった企業にとってのメリットばかりではなく、結果として顧客満足度の向上にもつながります。
たとえば、手作業での受注管理では短納期に対応することが難しくても、システム化をすることで受注から発送までのタイムラグを最小限まで短縮でき、短納期にも対応できるほどの余裕が生まれる可能性があるでしょう。
ニーズに応じて柔軟な対応ができるようになれば、顧客満足度が向上しリピート客の増加にもつながっていきます。
受注管理システムを選ぶ際のポイント
一口に受注管理システムといってもさまざまな製品・サービスが存在し、どれが自社にとって適しているのか判断できないケースもあるでしょう。
そこで、受注管理システムを選ぶ際のポイントをいくつか紹介します。
操作のしやすさ
受注管理システムは日々の物流業務を支える重要なツールです。
日常的に業務のなかで操作することを考えたとき、シンプルな操作方法で分かりやすいシステムが理想的です。
たとえば、見積書を作成するためにどのボタンを選択すれば良いのか直感的に判断できるか、少ない操作で簡単に作成できるかといった点を意識すると良いでしょう。
操作のしやすさはカタログやWEB上にある情報だけでは判断が難しいケースも多いですが、システムの提供会社によってはトライアルサービスの利用や、デモ環境で操作感を確認できるものもあります。
システムとの連携機能
受注管理システムだけを導入したからといって、すべての物流業務が効率化できるとは限りません。
重要なのは、受注管理システムとその他のシステムがどこまで連携できるかという点にあります。
現在、すでに顧客管理システムや在庫管理システムなどを運用している場合には、受注管理システムとどこまで連携できるのかを十分確認しておく必要があるでしょう。
システム連携が難しいと、一部の業務は自動化できているのにその他の業務は人手による作業が必要となり、業務効率化がうまく進まない可能性があります。
サポート内容やサポート体制の充実度
システムの導入後は、うまく動作しなかったり操作方法が分からなかったりと、さまざまな問題が発生しがちです。
そのような場合でも、丁寧なサポートをしてくれる受注管理システムを選ぶようにしましょう。
メールだけでなく、チャットや電話などによるサポートに対応しているか、障害などがあった際には出張サポートに駆けつけてくれるかといった点もシステム選びの重要なポイントになります。
WMSとは?物流における倉庫管理システムの導入メリットを解説
OTSはアパレル・ファッション・ジュエリーに特化した物流アウトソーシング専門会社
受注管理業務は取り扱う商品や商材によってもさまざまで、業界に特化した物流ノウハウが求められます。
物流管理システムを選定する際にも、自社が取り扱う商材の特性や業務内容を正確に把握し、最適な提案をしてくれるベンダーへ相談することが重要です。
もし、アパレルやファッション、ジュエリーといった製品を扱う企業や店舗において、受注管理を効率化したい場合にはOTSへご相談ください。
OTSはアパレルやファッション、ジュエリーに特化した物流アウトソーシングの専門会社であり、これまでさまざまなメーカーや卸売業者、小売店舗の物流業務を支援してきた実績があります。
アパレル商品は、個人の顧客に対して多品種少量の受注がメインとなることが多く、受注管理業務も煩雑化しがちです。そのような課題も、OTSへご相談いただくことでシステム化も含めた最適なご提案が可能です。
まとめ
メーカーや小売事業者にとって、数多くの注文が入ることは売上や利益向上に直結しますが、一方で物流業務が逼迫し人手が足りなくなるリスクもあります。
受注管理は物流業務のなかでも欠かせないものであり、小規模事業者のなかには手作業で管理しているところも少なくありません。
しかし、売上規模の拡大とともに手作業での管理は限界に達することも多く、自動化や効率化が求められます。
受注管理システムの導入は、こういった悩みを解決するための有効な方法のひとつであることから、働き方改革の実現や人手不足に対応するためにもぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
OTS PR
最新記事 by OTS PR (全て見る)
- 【オーティーエス】2025卒会社説明会開催中 - 2024年3月11日
- 不動在庫(デッドストック)がもたらすデメリットと対処法 - 2023年6月19日
- オムニチャネルとはどんな戦略?メリットを解説|成功事例も紹介 - 2023年6月14日
ブログの読者になる
メールで受け取ることができます。
関連記事
-

-
ファッションRFIDの活用方法
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部
-

-
会社説明会に参加して…
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部
-

-
ファッションアイテム用語について
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部
-

-
ファッション物流の入荷作業について
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部
-
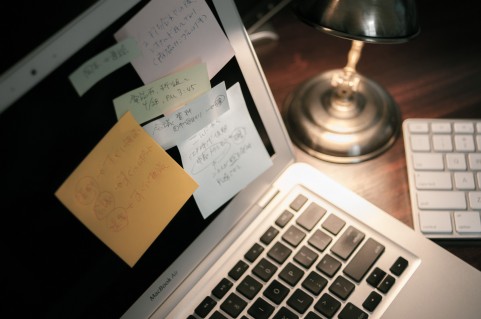
-
OTSへの期待を十二分に発揮できるように活動をはじめました!
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部