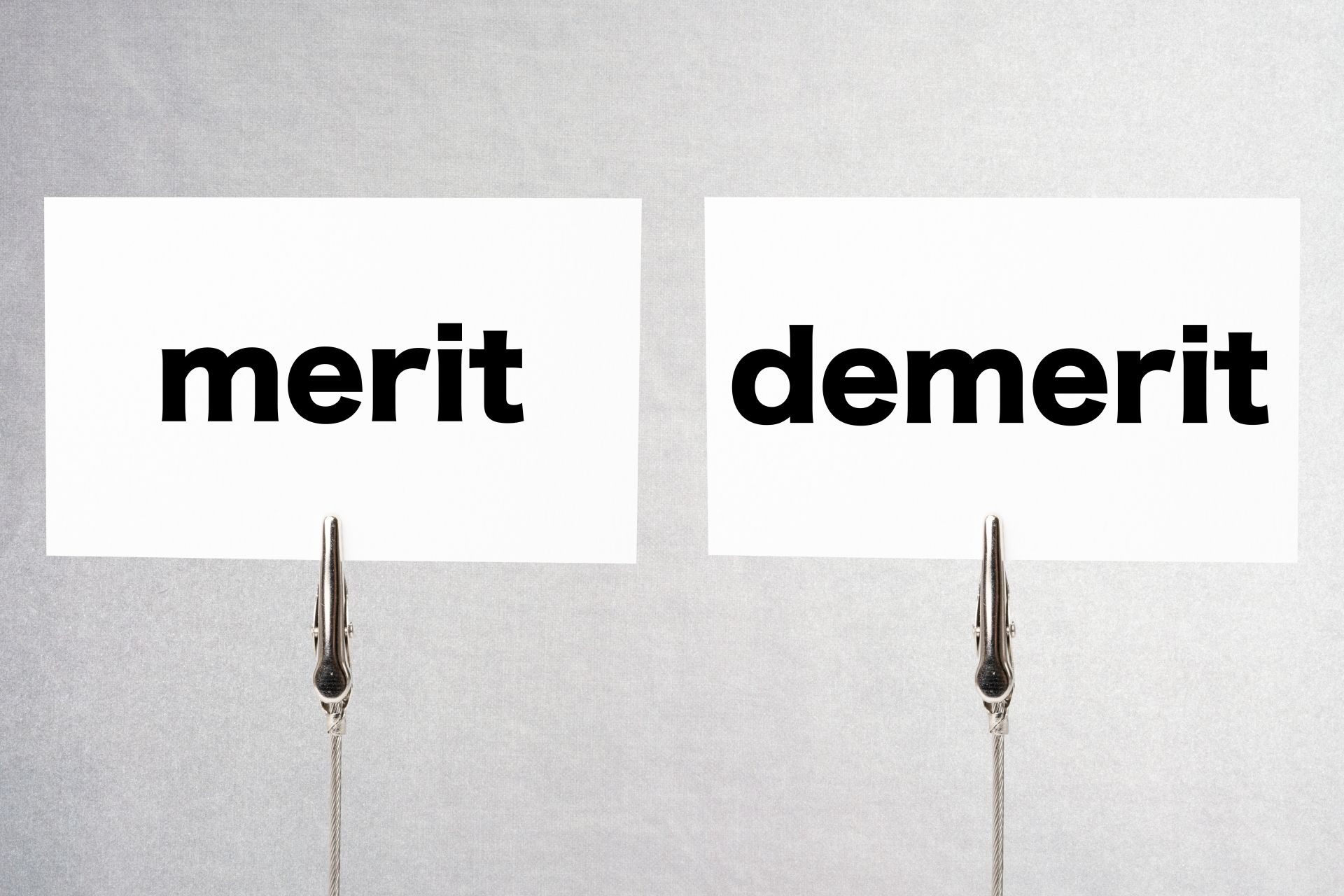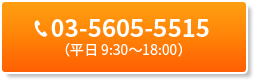先入先出法をわかりやすく解説|メリット・デメリットと活用事例を紹介
公開日:
:
最終更新日:2023/04/26
ファッション物流
さまざまな商品を取り扱うメーカーや卸売業者、小売業者にとって、在庫管理は欠かせない業務のひとつです。
一口に在庫管理といってもさまざまな手法がありますが、多くの物流現場で採用されているのが「先入先出法」です。
物流業務のノウハウや経験がない企業・担当者にとっては聞き慣れない言葉ですが、先入先出法とはどういった手法なのでしょうか。
本記事では、先入先出法の概要とメリット・デメリット、活用されることの多い例なども含めて詳しく解説します。
Contents
先入先出法とは
先入先出法は「FIFO(First-In First-Out)」ともよばれ、物流業務における在庫管理および棚卸資産の評価方法の一つです。
商品が入庫した際に、すでに保管されている古い在庫を商品棚の手前に移動させ、新しい商品は商品棚の奥に保管します。
これにより、商品を倉庫から出荷する際、もっとも古い商品から順番に出庫することができます。
また、仕入れのタイミングによって仕入単価が変わる場合において、先入先出法であれば古い商品から出荷されるため、棚卸資産の評価にあたっては新しく仕入れた商品から算出することとなります。
先入先出法は物流業務における在庫管理や棚卸資産評価の基本的なルールとして用いられているケースが多くあります。
特に、食品や医薬品といった消費期限がある商品を扱う場合などにおいて、保管時の品質劣化を防ぐために不可欠な手法です。
これ以外の商材においても、先入先出法は商品の品質管理や廃棄リスクの低減、棚卸資産の正確な評価などの点から重要な役割を果たしています。
先入先出法のメリット・デメリット
先入先出法は物流業務においてどういったメリットがあるのでしょうか。
また、デメリットとして考えられるポイントも紹介します。
メリット
先入先出法の主なメリットは以下の2点です。
廃棄や返品リスクの低減
食品や医薬品などのように、賞味期限・使用期限が短い商品において、適切な在庫管理ができていないと商品の品質が劣化し廃棄や返品のリスクが高まってしまいます。
先入先出法を採用することにより、期限が近づいてきた商品から順番に出荷でき、商品の廃棄や返品のリスクを低減することができます。
在庫コスト・在庫リスクの低減
期限が近い商品から出荷することにより、在庫の回転率が高くなります。
その結果、古い商品がいつまでも倉庫に滞留する心配がなく、在庫コストを削減することができます。
また、販売実績に基づいた正確な需要予測も可能になるため、在庫不足や過剰在庫を回避することにもつながります。
実態に近い棚卸資産の評価が可能
先入先出法では過去に入荷した順番通りに棚卸資産の評価を算定します。
実際の物流現場でも同様の順番で出荷することが多いため、帳簿上の棚卸資産と倉庫内の棚卸資産に乖離が起こりにくく、実態に近い棚卸資産の評価が可能となります。
デメリット
先入先出法のデメリットとして考えられるのは、以下の2点です。
在庫管理の複雑化・コスト増
先入先出法を運用するためには、商品の型番や商品番号などのデータ以外にも、製造日時やロット番号、消費期限、使用期限などの情報も管理しておかなければなりません。
取り扱う商品の種類や数が限られている場合には手作業での管理も可能ですが、物流の規模が大きくなるほどシステムの導入や管理にコストがかかります。
作業工数の増加
先入先出法を運用する際、物流現場での作業負担が増加するケースが少なくありません。
新たな在庫が入荷してきた際、古い商品を取り出した後、新しい商品の消費期限や使用期限を確認し、該当の場所に保管するという作業が物流現場で発生するためです。
ロケーション管理とはどんな管理方法?物流倉庫における役割やメリットを解説
後入先出法とは?
先入先出法とは反対の手法として、後入先出法があります。
これは「LIFO(Last In First Out)」ともよばれ、その名の通り最後に入荷した商品を最初に出荷するという在庫管理方法です。
先入先出法は期限が迫った古い商品から順番に出荷しますが、後入先出法では最後に入荷した商品から優先的に出荷されます。
先入先出法とは異なり、消費期限や賞味期限などを気にすることなく在庫の入荷順に発送するため、在庫管理が複雑化せず作業工数の削減にもつながります。
また、時間が経過しても商品の品質に影響を及ぼしにくい場合には、効率的な作業を実現するためにも後入先出法が好ましいでしょう。
ただし、後入先出法を採用することにより、財務報告における収益や利益のデータが歪められることがあるほか、在庫回転率が低下する可能性もあります。
このように、先入先出法と後入先出法はどちらが良い・悪いと単純に比較できるものではなく、商品の性質や目的に応じてどちらが適しているかを判断することが大切です。
先入先出法の例
実際の物流現場において、先入先出法はどのように運用されているのでしょうか。
代表的な業界の事例を2つ紹介します。
例1:食品・医薬品メーカー
賞味期限の短い食品を扱う企業において、もし後入先出法を採用してしまうと、つねに発送待ちの状態にある滞留在庫が発生し廃棄が出てしまいます。
そこで、つねに一定の品質を保つために製造日時が古い順番に出荷をする必要があります。
また、医薬品も食品と同様に有効期限が短い商品が少なくありません。
製造コストも高いことから、商品の品質を維持することはもちろん経済的な損失を抑えるために先入先出法は有効な在庫管理方法といえるのです。
例2:電子部品メーカー
意外に思われる方も多いですが、電子部品にも保管期間が定められています。
特に精密機器に用いられる半導体は、長期間にわたって保管していると品質が劣化するケースがあります。
食品や医薬品に比べると比較的保管期間は長いですが、それでも適正な回転率を維持し不良在庫をなくすためにも先入先出法が用いられることが多いのです。
受注管理システムとは?|導入メリットやシステム選定のポイントも解説
先入先出法以外の在庫管理・評価方法
物流現場において先入先出法は代表的な在庫管理方法ですが、実はこれ以外にもさまざまな方法があります。
取り扱う商材の種類や特性によっても最適な在庫管理方法を選択する必要があり、そのためにはさまざまな方法を理解しておかなければなりません。
そこで、先入先出法以外にどういった在庫管理方法があるのか解説しましょう。
個別法
個別法とはその名の通り、商品ごとに個別の在庫管理を行う方法です。
シリアル番号やロット番号などによって管理する方法のほか、アパレルやファッション製品などはカラーやサイズごとに管理する場合もあります。
個別法は商品ごとに在庫を細かく管理できるため、商品の特定や品質管理がしやすくなります。
一方で、効率的に管理するためには在庫管理システムの導入や管理者のスキルが必要となることも事実であり、運用コストが高くなる懸念もあります。
総平均法
総平均法とは、一定期間内に仕入れた在庫の仕入価格や在庫保有期間を考慮したうえで、在庫の平均単価を算出する方法です。
在庫の仕入価格や保有期間を正確に記録することによって適切な在庫評価が実現でき、財務諸表の信頼性が向上します。
一方で、短期的な需給変動に対応することが難しくなるほか、仕入単価や保有期間の記録には手間がかかるため、運用コストが増加する可能性もあります。
移動平均法
移動平均法とは、過去の在庫単価を参考にしながら新しい在庫単価を算出する方法です。
短期的な需給変動に対応できるほか、移動平均期間を調整することにより長期的な価格変動にも対応できます。
ただし、移動平均法では過去の在庫単価を参考にするため、新しい在庫単価が相場よりも高くなったり低くなったりする可能性があります。また、移動平均期間は適切な期間を選択しなければなりません。
売価還元法
売価還元法とは、在庫の単価を売上高に応じて調整する方法です。
市場の変化やトレンドの移り変わりによって需要変動が生じても、柔軟に単価を調整できるメリットがあります。
仮に需要が高まった場合、在庫単価が下がるため、より競争力のある価格設定も可能となるでしょう。
ただし、売価還元率を設定する際には適切な率を選択する必要があります。万が一売価還元率が高すぎた場合、利益率も低下するため経営に悪影響を及ぼす可能性があります。
最終仕入れ原価法
最終仕入れ原価法とは、在庫の原価を計算する際に最後に仕入れた商品の原価を基準に計算する方法です。
最終仕入れ原価法は仕入れ価格の変動に柔軟に対応できるのが特徴であり、需要の変動があった際にも迅速に適応することができます。
また、商品の原価を適正に把握できるため、経営の意思決定にも役立つでしょう。
ただし、在庫が長期間保管される場合、仕入れ価格の変動によって在庫の原価が大きく変化するリスクもあります。
低価法
低価法とは、同じ品目の中でもっとも低価格の商品の原価を基準に在庫の原価を計算する方法です。
在庫の原価を簡単に把握できる方法であり、手間がかからないため多くの企業で使用されています。
一方で、在庫商品の品質や仕入れ価格が大きく異なる場合、低価法を採用してしまうと在庫の原価が適正に反映されない場合があるため注意が必要です。
OTSはアパレル・ファッション・ジュエリーに特化した物流アウトソーシング専門会社
物流業務のなかでも在庫管理は基本的な作業であり、どのような商材を扱う場合であっても不可欠なものです。
近年、ECサイトの利用者増加に伴い、アパレルやファッション、ジュエリーといった製品をECサイトへ出品する事業者も増えていますが、これらの在庫管理では先入先出法よりも後入先出法を採用したほうが業務効率向上が見込める場合もあります。
ただし、すべてのアパレル製品やファッション小物、ジュエリー製品に後入先出法が適しているとは限らず、出品する商品の種類や売上規模によっても最適な在庫管理方法は異なります。
重要なのは、それぞれの事業者の規模や商品の特性などを理解したうえで、最適な在庫管理方法を検討することです。
これを実現するためには、アパレル・ファッション・ジュエリーの物流業務に関するノウハウや経験が不可欠なのです。
ECサイトへ出店している企業や店舗においては、物流のノウハウや経験が少ないケースも少なくありません。そのような場合には、物流アウトソーシング専門会社へ依頼するのもひとつの方法です。
OTSでは、長年にわたってアパレル・ファッション・ジュエリーの物流を手掛けてきた実績があり、先入先出法や後入先出法、その他の在庫管理方法も含めて最適な提案をさせていただきます。
まとめ
先入先出法は物流現場における在庫管理や棚卸資産評価のために、代表的な基本的な方法として採用されています。
返品や廃棄リスク、在庫コストの削減のほか、実態に近い棚卸資産の評価が可能であるというメリットがある反面、管理作業の複雑化や作業工数の増加といったデメリットがあることも含めて検討しなければなりません。
なお、先入先出法以外にもさまざまな在庫管理・棚卸資産評価の方法が存在し、それぞれの特徴を理解したうえで最適な方法を用いることが重要です。
物流業務のノウハウがなく、自社にとってどの手法が最適であるのか判断が難しいケースも多いと思いますが、そのような場合にはぜひ物流アウトソーシング専門会社であるOTSへご相談ください。
OTS PR
最新記事 by OTS PR (全て見る)
- 【オーティーエス】2025卒会社説明会開催中 - 2024年3月11日
- 不動在庫(デッドストック)がもたらすデメリットと対処法 - 2023年6月19日
- オムニチャネルとはどんな戦略?メリットを解説|成功事例も紹介 - 2023年6月14日
ブログの読者になる
メールで受け取ることができます。
関連記事
-
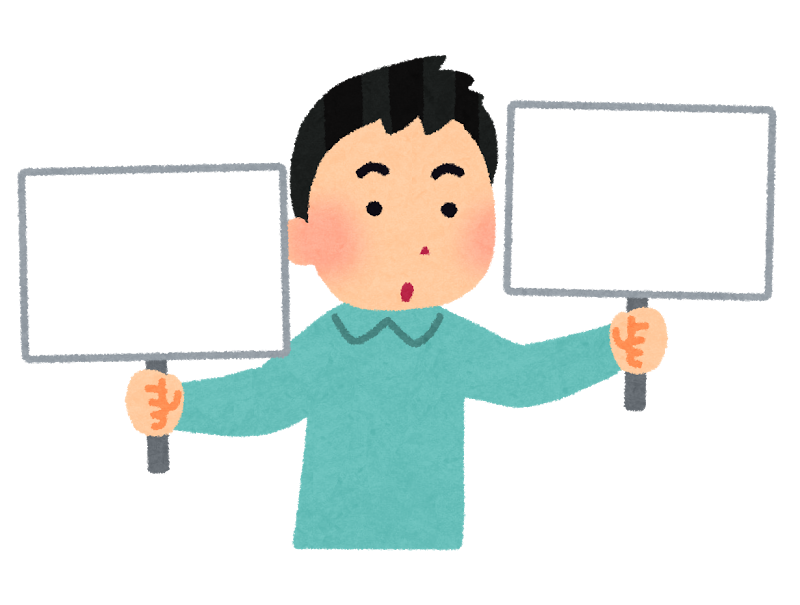
-
EC倉庫とアパレル倉庫との違い (前編)
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部
-

-
QCカスタマー業務担当者 インタビュー
 OTS PR
OTS PR
-

-
【物流に対する期待】
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部
-

-
物流改善を担当した方にちょっと役立つ知識
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部
-

-
カスタマーサービスのご案内
 OTS マーケティング部
OTS マーケティング部